筋トレのRM表の見方、最大重量を増やす計算方法について、プロトレーナーが解説します!
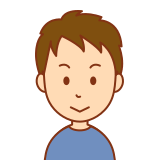
フィットネスジムによっては、印刷されて設置されているところを見かけることもあると思います。
RM表とは筋トレにおける最大回数を一覧にした表であり、RM表を見ることで怪我のリスクを抑えて最大重量を予測することができます。
ですが、多くの方がRM表の見方や計算方法について疑問があると思います。
なので今回は、筋トレのRMとは?最大重量を増やす計算方法と表の見方について解説致します!
筋トレのRMとは?最大重量を増やす計算方法と表の見方について解説致します!

RMとは
RMとは、「Repetition Maximum(レペティション・マキシマ)」の略で、「最大反復回数」のことです。
つまり、筋トレにおいて「最大何回連続で」できるかです。
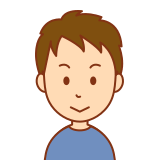
ベンチプレスで100㎏を1回だけ持ち上げられたら場合は、100㎏が1RMということになります。
◆筋トレで伸び悩みなやんだ時の打開策!4つのポイントについて解説
RM表の見方

RM表の見方を説明していきます。
それぞれBIG3であるベンチプレス、デッドリフトなどでRM表が異なりますが、見方は同じになります。
ベンチプレスのRM表
スクワット/デッドリフトのRM表
上の行がもう上がらない限界の回数、左がそのとき使っていた重さ(kg)です。
そして、その二つが交わるところがMAX重量になります。
RMの計算式:MAX重量=重量×{1 + (回数 ÷ 40)} ですが、これを毎回毎回計算していたら面倒だと思いますので、上記のRM表を使います。
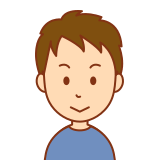
例えば、100kgを4回連続で持ち上げられるのであれば、110kgを1回持ち上げられるパワーがあることになります。
本来は、1回で上げられるMAXの重量を計測すれば、RM表は必要ありません。
しかし、MAXの重量にチャレンジすると、ケガのリスクもあるためなかなか計測することができませんので、このRM表が役に立ちます。
◆Big3の平均重量を男女別に解説!重量を伸ばすコツとは
目的別の確認方法

筋トレは、目的ごとに回数や重量が変わります。
目的は人によって様々であり、「競技力向上」「筋肥大」など目的に合わせたトレーニングメニューが重要となります。
ここでは、筋トレの目的別に解説していきます。
◆筋トレのノートの書き方とは!何を書くべきなのか、目的と合わせてプロトレーナー解説!
神経系の強化 1〜3RM
神経系の強化(最大筋量UP)が目的の場合、なるべく重い重量でトレーニングを行うことが重要です。
1〜3RMのトレーニングは神経系への刺激が目的となり、神経系の強化をすることで脳から筋肉への命令を伝達する神経が強化されます。
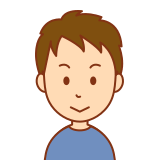
神経系を鍛えると、筋肉の力を100パーセント発揮することができるようになります。
筋肥大の強化 8〜12RM
8RM〜12RMでトレーニングを行うと、筋肥大を狙うことができます。
目安としては、10回上がるか上がらないか微妙な重さで動作を行うことがポイントです。
同じ重量で12回以上できるようになったら、少しづつ(2.5kg〜5kg)重量を重くしていきましょう。
筋持久力の強化 15RM〜
15RM以上は筋肉の持久力が向上に効果的と言われています
これは、水泳選手やサッカー選手のように持久力が必要な競技をしている人に有効なRM数です。
他にも初心者には、15RMくらいでトレーニングを行った方がケガもしにくいので安全にトレーニングすることができます。
最大重量を増やすコツ

最大重量を増やすコツとして、大きく4つご紹介します。
・可動域を広げる
・正しいフォームで行う
・柔軟性をアップさせる
・インターバルをしっかりとる
1つ1つ解説していきます。
可動域を広げる
可動域が狭い状態でトレーニングをすると、可動域が広い時と比べ筋肉への刺激が少なくなってしまいますので、筋トレ効率が悪くなります。
例えばスクワットは、なるべく深くしゃがみこんだ方が、筋肉への刺激が強まります。
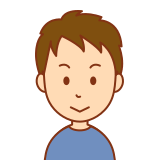
なので、筋肉の可動域が広げるためにも「お風呂上りにストレッチをする」「トレーニング前に十分に体を温めてほぐす」など、広げる努力を行いましょう。
◆筋トレは可動域で変わる。超効率で鍛える「可動域」の重要性
正しいフォームで行う
フォームにこだわり過ぎてしまうあまり、重量に伸び悩むことがあります。
もちろん、ある程度正しいフォームを身につけることは大切です。
正しいフォームでトレーニングしないと効かせたい筋肉に効かせることができず、トレーニング効率が悪かったり、ケガをする恐れがあります。
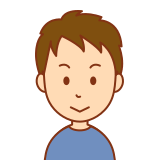
なので、「最大重量のみを目指すのか」「筋トレ効率を上げることを目指すのか」、目的に応じてフォームの意識を変えるようにしましょう。
柔軟性をアップさせる
体の柔軟性を高めることで、筋肉本来の力を発揮することができるようになります。
例えば、デッドリフトの場合、もも裏の柔軟性が上がると、背中と足の両方の筋肉を使うことができるので重量が伸びやすくなります。
スクワットの場合は股関節の柔軟性が上がることで、下半身全体で重さを上げることができます。
▼ケガの予防にはマッサージガンがおすすめ!
◆筋トレのウォームアップは必要?効果や重要性についてジム店長が徹底解説!
インターバルをしっかりとる
インターバルを取ることで筋肉を休ませることができ、次のセットでも高重量を扱うことができます。
実際に、インターバルを取ることで、筋肥大や筋力向上にも効果的であることが多くの研究で明らかになっています。
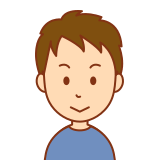
MAX重量に挑戦するのであれば、3〜5分程度の充分なインターバルをとって神経系を回復させてから行いましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、筋トレのRMとは?最大重量を増やす計算方法と表の見方について解説致します!
RMとは、「最大反復回数」のことを指し、最大何回連続でできるかです。
ここで重要なことが、筋トレは目的によって扱う重量や回数が変わってきます。
なので、「目的に合わせた筋トレ」をするようにしましょう。
・神経系の強化(最大筋力UP) 1〜3RM
・筋肥大の強化 8〜12RM
・筋持久力の強化 15RM〜
最大重量を増やすコツは以下のものがあります。
重量が伸び悩んでいたら、試してみてください。
・可動域を広げる
・正しいフォームで行う
・柔軟性をアップさせる
・インターバルをしっかりとる
▼ケガの予防にはマッサージガンがおすすめ!
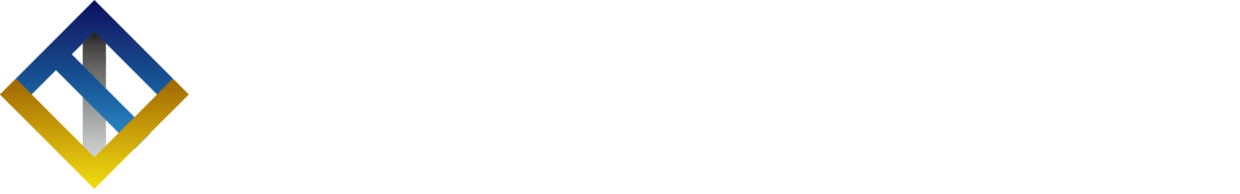

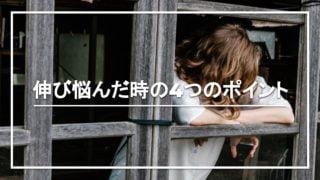

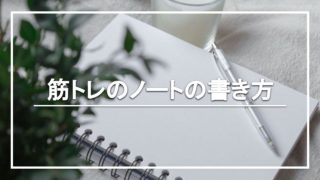




コメント